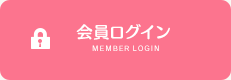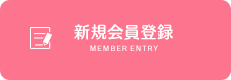令和7年度NICUにおける在宅移行支援者育成研修のご案内
周産期医療・看護の進歩とともにNICUで出生した新生児の救命率は向上しています。一方で、NICUにおける長期入院児は増加し、退院後も、多くの子どもは、医療的ケアや*1、他、成長発達していく過程において、様々な支援を必要としています。
そういった対象が、退院後も家族としての関係性を構築しながら、地域において安全に安心して生活していくためにも、子どもの出生時から支援する、NICUにおける看護職の役割はとても重要です。
診療報酬においても、2016年度改定で、退院支援加算3が新設され、以降見直しがなされ、入退院支援加算3と名称が変わり、2020年度には、この加算を取得する施設基準要件として、担当する看護職が適切な研修をうけていることが明記され、現在、公益社団法人日本看護協会等において研修が行われています。
厚生労働省等においても、様々な医療的ケア児等とその家族に対する支援施策が示されています。しかしNICU看護職が学ぶ機会が十分整備されているとはいえないのも現状です。
そこで、本学会においても、NICUから在宅への移行支援のさらなる質の向上にむけて、専門的な知識・技術を持ち実践できる看護職の育成をめざして、本研修を企画しました。
この研修では、よりよい支援のためにも、退院後の家族の生活をできるだけ具体的にイメージできること、関連する多職種の役割を理解し、お互いの専門性を活かした連携を実践できること、そして、生まれてからのNICUにおけるケア、例えばファミリーセンタードケアの実践そのものが退院後の家族の生活の質に大きく関わることなどを理解していただきたいと考えて企画しております。
また、本研修は、診療報酬上の退院支援加算3の施設基準に定められている「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」に対応しています。
子どもを含めた家族への支援の質向上、そして診療報酬の算定のためにも、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
*1 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことであり、全国の医療的ケア児(在宅)は、約2万人〈推計〉である。
https://www.mhlw.go.jp/content/000981371.pdf
研修の概要
| 研修名 | NICUにおける在宅移行支援者育成研修 |
| 研修目的 | NICUから在宅への移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護職の育成 |
| 研修目標 | (1) 在宅での生活(子どもとの生活、その中でのケアなど)について具体的にイメージできる
(2) (1)に基づいた支援を自立して実践することができる
(3) (2)のための、自施設の現状と課題、それについての行動計画を作成できる |
| 開催方法 | ・ 動画配信および集合による研修 ・ 訪問看護ステーション等での実習 |
| 応募者の要件 | 新生児集中ケアに3年以上携わっている看護職 |
| 募集定員 | 100名 |
| 受講料 | 会員 11,000円 非会員 22,000円 |
カリキュラム
1. オンデマンド研修
「NICUからの在宅移行支援のあり方」 内田 美恵子
「NICUからの在宅移行支援における看護職の役割」 中村 典子、室加 千佳
「NICUからの在宅移行支援に関する現状と課題」 田村 正徳
「在宅移行後の継続ケアに必要な知識−1−」 有馬 夕紀、稲垣 藍、小泉 恵子
「在宅移行後の継続ケアに必要な知識−2−」 小泉 恵子
「日本看護協会版『NICU/GCUにおける小児在宅移行支援パス』の活用」 ワーキンググループ委員
「NICUにおける在宅移行の実際 ―事例報告―」 松村 好野
2. 集合研修
「在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応方法」 奥寺 さおり
「多職種による模擬退院支援カンファレンス場面の再現(演習)」
平原 真紀、稲垣 藍、有馬 夕紀、小泉 恵子
※詳細は研修概要PDFをご覧ください。
研修受講の流れ(予定)
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 申込期間 | 動画研修配信期間 | 集合研修 | 修了証発行 | ||||
| 実習施設の選定/交渉・実習・課題 | |||||||
1. 申込
| 申込期間: | 2025年5月12日(月)〜2025年6月30日(月) |
| 申込方法: | ページ下部にある申し込みフォームより期日内にお申し込みください。 受講料は事前入金制です。 いかなる理由によるキャンセルでも返金できかねます。 |
2. 動画研修
配信期間: 2025年7月1日(火)〜2025年10月31日(金)(予定)
- 配信期間中は何度でも研修動画の視聴を行えます。
- 配信期間内に視聴が完了しない場合、集合研修に参加はできません。
修了証も発行できかねますので、ご容赦ください。
3. 実習: 訪問看護師との同行訪問
| (1) | 所属長とともに、実習を受けてもらう施設を決める。 |
| (2) | 規定の用紙に沿って、実習計画書を作成する。 |
| (3) | 実習計画書に基づき、訪問看護師による、NICUから退院した子どもの訪問に同行する。実習は、動画配信研修をすべて受講した後が望ましい。 |
| (4) | 規定の用紙に沿って、実習報告書を記載する。必要時所属長の確認を得る。 |
| (5) | 実習報告書は集合研修時に持参し、研修終了後提出する(必要時コピーをとる)。 |
訪問看護師との同行訪問ができない場合は、下記方法(例)で、NICUから退院した後の家族の話を聴く機会を得る。
- 退院後の外来等で面談する。
- 退院後の親の会など退院後に家族が集まる場に参加し、個別に面談する。
※いずれの場合も、部署の管理者、主催者及び面談する場合は、その家族本人に、実習の目的や話してくれた内容の取り扱い等について説明して了承を得る。
※実習計画書および報告書は訪問同行と同様に記載をする。
4. 課題: 自施設における在宅移行支援の現状と課題について
| (1) | 規定の用紙に沿って、自施設(自部署)の現状と課題について記載する。 |
| (2) | 記載した用紙は集合研修時に持参、研修終了後提出する(必要時コピーをとる)。 |
| (3) | 記載上の留意点
|
5. 集合研修
| (1) | 日時 2025年11月13日(木) 9時20分〜17時00分(予定) |
| (2) | 会場 アトムメディカル本社 会議室(本郷三丁目) |
| (3) | 留意事項
|
問い合わせ先
日本新生児看護学会 事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F 株式会社クバプロ内
TEL : 03-3238-1689 / FAX : 03-3238-1837 / E-mail : jann@kuba.jp